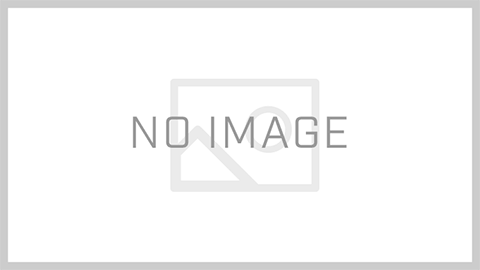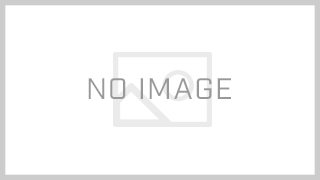技術はすべてではないけれど、
あれば自分の感じ方をもっとよく知ることができる。
今回も美術に関するお話です。
小説書きなのに、最近そんなところに浮気しています。
そのうち絵を描くんじゃないか、と自分でも思うのですが、
今のところは面倒なのでやらないでしょう、きっと。
さて、先日はこんな本を読みました。

たまに美術館に行っても、どうにも楽しみきれていない感じがして、
少しは知識をつけようと思い立ち、読んだのでした。
結論から言うと、非常に参考になる本です。
一方で、技術がすべてではないともあらためて思わされるものでした。
構図や配色は、きっと絵描きにとっては基礎的な技術なのでしょう。
しかし、私のような素人にとっては、馴染みのない世界です。
だから、色にどんな効果があるか、斜めの線にどんな効果があるか。
比較して初めて理解できることも多かったです。

ゴヤ「1808年5月3日 プリンシペ・ピオの丘での銃殺」
本にも挙がっていたこの絵。悲劇的な場面が描かれています。
正直、あんまり直視したくない類のものです。
なぜそう感じるのか。
ひとつは撃たれる男の表情が細かく描かれていて悲壮だから。
そして、その表情が足下のランプに照らされてくっきり映るから。
さらに、銃口という死の予感を思い切り突きつけられているから。
視線と銃口が交わるという構図が、最大限効果を生んでいるわけですね。
この男の視線がたとえば上に向いていたらどうでしょう。
悲劇的でしょうが、なんとなく間が抜けている感じになり、
悲壮感は出てこないでしょう。
構図というのは、作者の思いを的確に伝えるには、
用いるべき技術のひとつなのですね。
一方で、技術がすべてではない、とも思ったのがこの絵でもあります。
元の絵は強烈なインパクトがあったせいか、
その後同じ構図で別の画家が描くということもあったようです。
その中で、本書に「失敗作」として挙げられていたのがこの絵。

マネ「皇帝マキシミリアンの処刑」
先ほど私が書いたような状態です。
撃たれた直後なのでしょう、男の顔が上に向いています。
また、貴族のような人が無表情で相対しているのもなんだか変です。
ぱっと見たとき「間が抜けているなあ」と強烈に感じました。
ヤバイ出来事なのに、そこに悲壮感がない。
そういう意味では確かにこれは「失敗作」と言えるかもしれません。
でも、そうわかっていても、私の中では、
マネの方も強烈なイメージとして記憶に残っています。
「悲劇的な場面なはずなのに、間が抜けている」この矛盾。
作者が狙ったことではないのかもしれない。
しかし、もしかしたら狙ったことなのかもしれない。
あからさまに間が抜けているということは、
この銃殺には滑稽な背景があるのかもしれない。
矛盾が、私の中でストーリーをどんどんと作っていくのです。
そうやって誰かの心の中に何かを残したとき、
その作品ははたして「失敗作」と言えるだろうか?
狙ったものではなくても、人の記憶に残れば、
それはそれで価値のあることではないでしょうか?
技術は確かに作品を読み解くためのひとつの手段です。
しかし、その技術の使い方が正しくなくとも、
価値が生まれることもある。
私が思うのは、むしろ自分の感情のありかを探すために、
技術の知識を利用すべきなのではないかな、ということです。