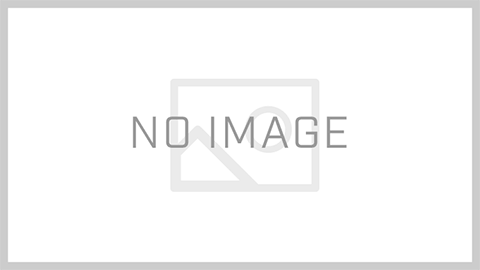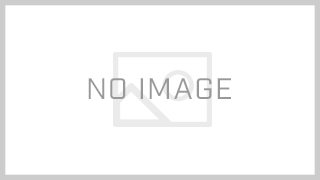先週に引き続き、「翻訳」のお話。
別に誰に見せるというわけでもありませんが、
「星の王子様」の英語版の翻訳を練習がてら始めました。
「星の王子様」は小学生のときに読んで以来、
私の中で大事な一冊になっていました。
というのは、丁寧な翻訳が小学生でもわかりやすかったからです。
文庫ではなく、単行本版で読んだとき、
ふわっとした雰囲気で描かれたそれが本当に好きだった。
冒頭の「象をのんだうわばみの絵」のくだりは特に。
それから時間が経ちました。
当時実家にあった単行本も、今では行方知らず。
社会人になってあらためて文庫版を買いました。
でも、それを読んだとき、
色々なものが「損なわれている」ように感じてしまったのです。
自分の記憶の本とは雰囲気が決定的に違いました。
冒頭から、すぐにそれがわかってしまったのです。
あの絵が「象をのんだ大蛇」という説明になっていたから。
その表現をはじめとして、その文庫版の訳は、
ふわっとした雰囲気が消えてしまい、
もっと地に足が着いた大人の本になっていました。
元々の「星の王子様」がどんな雰囲気の本かはわかりません。
私はフランス語が読めませんから。
しかし、王子様をはじめとした登場人物たちは、
どこか現実離れしていて、美しい心を持っているひとたち。
地に足が着いていてほしくはなかったのです。
思い出補正があるのは間違いないのですが、
私は小学生のときに読んだ本の雰囲気を
もう一度求めたくなりました。
だから、英語の練習もかねて、英語版を翻訳する、
そんなことに挑戦しています。
でも、自分がやってみて、
初めて翻訳の難しさを思い知らされています。
「英語が読める」ことと「日本語にする」ことは、
次元が違うと痛感しています。
たった一文字の「I」を日本語にどう置き換えるか?
登場人物たちの特性、文体の雰囲気、作品のテーマ。
いくつもの要素を総合的に判断して、
「僕」にするのか、「ぼく」にするのかを決めていく。
先週の「MGS4」もそうですが、自分のフィールドで書くことは、
自分のフィールドの特性を活かす判断をすることになる。
翻訳とは、元の作品の意図を正確に読み取った上で、
「自分の作品」として仕上げていく覚悟がいる。
今、翻訳をしている私も同じことを求められているのでしょう。
「思い出の作品に近づける」ことは、
少なからず私の中の世界観を反映させることですから。
しかし、同時に元の作品の世界観の中に生きることでもあるから。
そんなことを悩みながら、
こつこつと誰にも見せない翻訳を続けています。
自分が満足できる訳になるまでには時間が必要そうです。