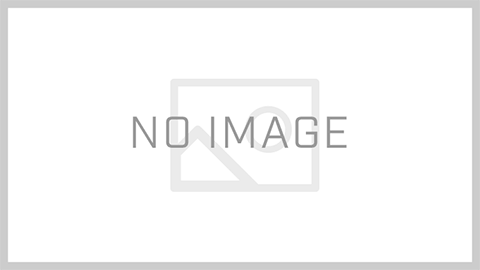先日Switch版「ゼルダの伝説 夢をみる島」をクリアしたんですよ!(相変わらず今さらってタイミングでクリアしがち)
元々はゲームボーイのゲームなので、Switchのソフトにしてはボリューム不足と言われることもあるようですが、私はそう感じませんでした。まあ、確かにゲーム性のやりごたえは少ないかもしれません。でも、この作品独特の雰囲気、そして、クリア後の一抹の寂しさは唯一無二です。この独特の余韻、まさに、「長くて美しい夢を見た」あとのような。
夢から覚まそうとする自分が悪いのか?
この「夢をみる島」は、ストーリー的に他のゼルダ作品と一線を画しています。リンクが世界を救うヒーローではない、というところです。他の外伝的な作品、例えば「ムジュラの仮面」だって、リンクは世界を救うために奔走します。でも、この作品は違います。
ストーリーの結末については、うん、もう20年以上前の作品なので、さすがにネタはバラしていいでしょう。物語の舞台となる「コホリント島」は実は夢の世界で、リンクがボスを倒すと夢として消えてしまうという流れです。ある意味で残酷な運命を、自分の手で引き起こすのです。
もちろん私も知っていましたので、「まさか!」みたいな驚きはありません。それでも、物語を進めていくと「この島がリンクによって消えてしまう」ことを否応なく感じさせてくるんですよ。それがボスキャラクターを倒した直後、痛々しい姿が見えるタイミングでも言われるから余計に罪悪感が増します。わかっていながらも「自分が悪いのか?」と胸を抉られるようでした。
最後に「風のさかな」がら夢から覚めることを肯定的に捉えてくれるのである程度救われつつも、やはり島が消える様を見るのは悲しい、わかっていてもね。「地味なしんみり感」にやられました。当時の制作陣はどういうつもりでこんなストーリーにしたのでしょうね。当時のゲームボーイの容量という制約の中で、切ない物語を紡いだことに脱帽です。
短い言葉でも、キョーレツ!
制約でいえば、セリフが少ないながらも、コホリント島で出会う個性豊かなキャラクターたちも個性豊かというか、全員クセつよつよですよね。ものごとをズレて捉えている感じ、あります。
例えば、うるりらじいさん。進行のヒントをくれる、よくあるお助けキャラなのですが、なぜか直接話してもまともに会話できず、なぜか外の電話ボックスからならヒントをくれるという。なんでひと手間かけさせるキャラにしたんだよ!(あと、電話ボックス内のBGMもクセ強)
パパールも出会った瞬間から、山で遭難することを予告してくるし。いきなりメタ発言やめてもらえますか??? その時点でもだいぶふざけていると思いますが、「遭難した時はよろしく!」とまで言ってくるのはもはや笑うしかありません。(鼻で)
そんな感じで、個性が強いというか、なんだったらちょっと厚かましいくらいにまで感じるからこそ、サブキャラクターなのに妙に記憶に残ってしまうんですよね。その後のゼルダシリーズで「サブキャラクターが個性的」と言われることが多いと思いますが、その伝統はこの「夢をみる島」から始まったのではないかな、と感じました。
その中で唯一まともな(方の)キャラクターのマリンは、(まともに)印象に残りました。もちろん、リンクとの絡みが多いというのも理由ですが、彼女だけがこの島の中で異質な考え方を持っているからですね。それは「島の外の世界を知りたい」ということであり、「風のさかなの夢から覚まそう」としたことです。他の島の人々は外の世界のことを考えたことすらないようです。彼女がなぜそのような考え方を持つに至ったのか? 明確には語られませんが、想像の余地はとても多いと思います。
直接的なきっかけは、リンクが島の外から流れ着いたことでしょう。「外の世界」に人がいることを初めてマリンが明確に実感した出来事だと思います。そこから彼女が色々考えて行動していくことはすんなりと私も理解できました。

しかし、なぜ、「風のさかなの歌」を自ら歌おうとするのか? 特定の楽器が必要とはいえ、その歌は風のさかなを目覚めさせる歌です。前述した通り、風のさかなを目覚めさせることは、夢の世界の消失を意味しており、それはマリン自身の消滅を意味することでもあります。
そして、マリンはその意味を理解した上でそうした行動に出ています。リンクと波打ち際で話しているところや、リンクがすべての楽器を手にしたのちに別れ際に口にする「忘れないで、私のことも」というセリフから明らかです。彼女にどういう意図があるのか? それはゲームでは明確に語られておらず、我々プレイヤーに委ねられる領域なのでしょう。
ここからは私の想像になります。おそらく、マリンは島の真実をほとんど正確に把握しているのだと思います。風のさかなが長く夢を見続けることによって、悪夢の世界に変わっていくことも知っていたのだと考えます。だから、彼女は自身が消失するとわかっていても、悪夢に変わる前に夢を終わらせることを、そしてリンクを現実の世界に戻すことを決意したのだと思います。
言葉で書くのは簡単です。でも、一度はリンクと一緒に外の世界へ行きたいと思っていたはずなのに、彼女はその「夢」を諦めて別れを告げた、と考えると切なさに胸が締め付けられます。
夢と現実、入れ子のように
最後に、風のさかなのセリフ。この物語の核心をついていながら、解釈が難しいと感じました。
まずはこの二つ。
「夢は覚めるもの」
「思い出は現実に残る」
うん、ここまではよく聞く言葉ですね。他のフィクションでもよく出てきますし、なんだったら私もそれをテーマに物語を作ったこともあります。

でも、少し変わっているのはその次の言葉ですね。
「その思い出がいつか夢になる」
この最後の言葉が、私を無限回廊に誘ってしまいます。文字だけ読むと、ある種の「入れ子構造」を示していることになりますよね。夢を見たことは、現実の思い出となり、思い出が夢となり、またそれが現実の思い出となり……という。ほら、まさに無限ループに囚われた感覚でしょう?

人ひとりの時間だと納得できることもあります。ある長い夢を見て、夢から覚めても夢を見た記憶は残っており、その記憶が次の夢へと導くと。でも、それだけではないような気もするんですよね。
あるいはこの「夢」をゲーム作品と置き換えてみますか? つまり、ゲームは虚構だけれど、プレイした思い出は我々の現実に残り、やがて我々のうちの誰かが新しいゲームを作っていくような。まさにこの「夢を見る島」がその構造に当てはまります。または、「未来への希望」のことでもいいかもしれません。その場合はゲームと同じような言い方ができると思います。
いずれにせよ、風のさかなのセリフは色々な解釈のしようがあります。当時の制作者がどこまで考えていたのかはわかりませんが、深遠な意味が込められているようにすら感じます。そう考えると、やっぱり深みにハマっていってしまって、自分自身でこのゲームの印象を強めてしまいますね。
改めて、このゲームの印象は「終えてからこそ深まる」というものでした。遊んでいる間よりも、終えてからあの短いセリフの意味を考えることにこそ価値があるような。それがあのモノクロの、めちゃくちゃ画面が小さいゲームボーイの中で、こんな心揺さぶられる物語が紡がれたことに、ただただ驚きました。もちろん、Switch版ならではの美しさもありながら、なんという夢を見させるのでしょう。わたしは、もうしばらくこの余韻に浸りたいと思います。